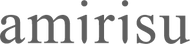石徹白洋品店: サステイナブルな環境と
地域をめざして - Issue 20


日本には昔の暮らしが残存する山村がまだ各地に点在しています。そのひとつは本州のほぼ中央あたりに位置する、岐阜の山奥の小さな村、石徹白(いとしろ)です。
急速に過疎化が進む地域にあるこの小さな村へ、9年前に友人夫婦が移住しました。以来、3人の小さな子供たちと一緒に新しい暮らしかたを模索しています。その鍵となったのは、サステイナビリティと手仕事です。
その村は高い山々を超えた奥にひっそりと隠れており、近くに町などないそんな僻地に今でも住んでいる人がいるなんて驚くばかりです。さらに驚くべきは、この村の歴史は縄文時代に遡るということ。日本三名山のひとつ、白山の麓に位置するこの村は、古くから神道の流れをくむ白山信仰の中心地でした。北の空を見上げると、いつも目に入る白山連峰。冬の間はその名の通り、真っ白な山が石徹白を見下ろし、見守っています。この山に参る人々は、いつの時代にも日本中からやってきました。白山の登山口を守る神社には地域の大名たちが献上品を送り、織田信長から送られた品も伝えられるのだとか。しかし、それは過去の話。近年、石徹白の人口は急速に減り、現在は250人ほど。高齢化も進んでいます。友人夫婦を訪ねて7年前に初めて訪れたとき、目に着いたのはたくさんの空き家でした。


夫の平野彰秀さんとは都市計画やコミュニティ開発を学んだ大学院で知り合いました。その後、5年くらいしてコンサルティング会社に就職したときに、偶然同時期に入社した平野さんと再会。数年間同僚として一緒に仕事をしました。当時の私はいつかまちづくりに関わる糧になるかもしれないとコンサルティング会社を選んだのですが、彼もそのうちUターンして地元岐阜のまちづくりに関わるつもりなのかなと思っていました。
でも、石徹白への移住を最初に決めたのは奥さんの馨生里(かおり)さんのほう。彼女も岐阜出身ですが、二人とも石徹白は身近な土地ではなかったのです。大学卒業後、東京で就職していた馨生里さんは、週末になると岐阜市のまちづくり団体の活動などに参加するようになります。そのグループで訪れた場所の中に、石徹白はありました。その場所の歴史や、水が豊富なこの地域では小水力発電の可能性があること、石徹白はそれにぴったりの場所であることなどを知りました。それはもちろん可能性があるというだけでしたが、石徹白を一目で気に入ってしまった馨生里さん、それをどうしても実現したいという強い思いが芽生えたのです。当時24歳。地元の人を説得し、補助金をもらって小水力発電機を設置する活動をスタートさせました。
その話を聞いた私は、他所から来た、しかも若い女の子の提案をそんな田舎の人に話しても、受け入れてもらえるはずがない、と驚きました。もう何十年も、なんにも新しいことが起こったことのないような、人里離れた静かな田舎の小村。よそ者からあれしろ、これしろと指図されたことなんてなさそうな人たちです。
しかしながら、石徹白の人々は違いました。この場所の特殊性は、古くから日本中より白山の登山者を受け入れてきたこと。よそ者が常に村を訪れ、白山を目指す前後の数日、村の人々がもてなしてきたのです。それに加え、急速に過疎が進んでいくことの危機感があったと言います。
同じ活動を通じて石徹白を知った平野さんも、馨生里さんの小水力発電機設置を手伝うことに決めました。
最初は通いながら活動をしていた馨生里さんですが、山奥の石徹白に移住しようと決めてから、2年間洋裁学校に通って仕立てとパターン制作を学びました。収入源として誰かに雇ってもらうのが難しい以上、自分で何か作ってお店をやるしかないと考えたからです。また、持続可能な社会を考えたとき、私たちの生活に欠かせない衣食住のなかで、食や住と比べてもファッションだけ遅れを取っているように感じていました。そこで、ユニークでサステイナブルな商品を手作りし、小さなブティックを開いたらどうか、という計画でした。
もともと洋裁は得意ではなかったそうで、学校に通った2年間は苦労の連続でしたが、なんとかやり遂げました。馨生里さんが着々と準備を進める一方で、平野さんは地域再生機構というNPO法人に参画し、小水力発電導入や地域づくりのコンサルティングをスタートさせました。2011年秋、満を辞して二人は石徹白に移住しました。
2011年は東日本大震災のあった年。多くの若いカップルや家族が、大都会から地方へ移住して行きました。これを機に地域を活性化させようという地方自治体もたくさんあったようで、移住者の受け入れも加速しました。もしかしたら、そんなタイミングもあったのかもしれません。移住後、平野さんは本格的な小水力発電機の導入を視野に入れたパイロットプロジェクトを石徹白でスタートさせ、今では4台の小水力発電設備で必要電力の230%を賄っているそうです。(余剰電力は北陸電力に売電され、設備投資費用の返済と農業支援に充てられています。紆余曲折の経緯はここでは語りきれないので、ぜひ取材記事などをご覧ください。全国でも稀なケースでとても注目され、ドキュメンタリー映画にもなりました。)
馨生里さんはといえば、計画通り、自らデザインした服作りを始め、オリジナルウェアや仕入れた手仕事の商品を集めた石徹白洋品店を翌2012年の春にオープンさせました。アトピーに悩まされた経験から、できるだけ肌や環境に優しい素材にこだわり、洋服にはオーガニックコットンなどを使うことに決めました。制作から販売までを一人でこなすのは大変でしたが、無我夢中でした。

それ以来、会社は次第に成長し、今では12人の従業員を抱えるまでになりました。数名のフルタイムと、それぞれの可能な範囲で働くパートさんです。主力商品は草木染めや藍染された、たつけやはかまと呼ばれる数種類のパンツ。そのほか、越前に伝わるシャツをベースとしたブラウスやチュニック、ワンピース、そしてスカートなど。使用する生地は丁寧に作られた上質の素材や、工場で廃棄されるところだった布を買い受けたものなど。地域で機織りされた布から作られる商品も生まれました。夏の間は畑では藍をはじめ、様々な染料となる植物を育て、染や縫製作業は一年中続きます。石徹白に根ざした事業を目指すうえで転換点となったのは、この地方に古くから伝わる野良着との出会い。先祖代々石徹白に住むご近所さんの倉から発見された、たつけと呼ばれる農作業用の和服のズボンです。
着物の動きにくさを考えてみたら当然なのですが、昔の人も農作業などをする時にはズボンのようなものを履いていたのです(私も考えたことがありませんでした)。リサーチを始めた馨生里さんは、たつけのような野良作業用の和服ズボンの様々なバリエーションが全国に存在すること、何百年も前から作られていたこと、そしてブラウスのようなトップスも日常着として着られていたことを発見しました。(戦時中のもんぺは、政府が洋服のパンツをもとに型紙を作って配ったそうで、実は和服とは関係がないそうです。)

たつけは昔、武士や忍者が着ていた袴やズボンの一種で、民衆のニーズに合わせて発展を遂げたものです。着物用の反物の幅(通常36~39cm)で制作できるようデザインされています。普通のスボンの型紙では股上の幅がグッと広がっていますが、36cmしかない反物ではこの幅をとることができません。幅の狭い布でどうやって動きやすいズボンを作ったらいいのか。昔の人々が工夫を重ね、パーツをつなぎ合わせて同じような形を実現していった様が伺えます。そして、洋裁だったら斜めやカーブにカットされた色々なパーツによって、たくさんのゴミが出ます。変な形をしているので、残りを余すことなく使うのはとても難しい。でもたつけは反物を無駄なくカットしたパーツを縫い合わせて作られるために、布は1cmも捨てられることはありません。民衆にとって織物がそれだけ貴重だったということでしょう。そんなふうにして作られたたつけは、色褪せれば重ね染され、解いて他のものに使われ、布がボロボロになるまで大事にされました。馨生里さんが見つけた他の野良着も、同様に作られていたものばかりでした。こういった伝統的な野良着がとても実用的で動きやすく、一切の無駄がないことに感動し、それを生み出した昔の人の知恵を伝えていこう、そして自分はこれを作っていこうと決めました。野良着をベースにした服作りを始めてからの石徹白洋品店では、布のゴミはほとんど出なくなりました。残った布もすべて長方形なので、パッチワークで小物などを作るのに使われています。
地域の古家に残されていた数着を詳しく研究しながら、現代の私たちが日常着として着られるようにするための型紙づくりや、サイズ展開の作業が始まりました。昔の人は古い野良着などを取っておかないので数も少なく、また、どのようなサイズ感になるのがいいのかも見極めるのが難しかったそうです。たくさんの試作品を作って、型紙を作り上げました。

一方で、地元で手に入る植物を使って、使用する布地を草木染めする試みもスタートしました。自然の草木、特に杉の葉などなら、いくらでも手に入ります。しかもタダ。小水力発電のプロジェクトが成功したことで石徹白も次第に知られるようになり、若い夫婦の移住者が少しずつ増えてきたので、染め作業を手伝ってくれるパートさんも雇えるようになりました。
藍染を始めるきっかけになったのは、自宅の隣にショップスペースを備えた新しい染め用の工房を建てようと計画していた時期に、ある藍染の職人さんを紹介されたことでした。近くの郡上大社で50年以上も藍を染めてきたという方です。リタイアして数年経ち、50年使ってきた藍染の甕を譲ってくれるという話に。
先日の取材で地域のお年寄りからもらい受けたという藍染の上着を私も見せてもらいました。それは藍が染まっていない部分だけがきれいに虫食いにあっているものなのですが、それもあって藍染の素晴らしさを実感していた馨生里さん。もちろん興味はあるけれども、50年来の甕をもらい受けるような覚悟は全くなかったと言います。でも断れる雰囲気でもなく、工務店の人と甕を引き取りに行くことに。藍染の甕とはどんなものかよくわかっていなかった工務店の担当者。なんと掘り出し作業の際に甕を割ってしまったのです。激怒する職人のおじいさん。そこで馨生里さんは新しい甕を購入し、割れた甕を新品の甕の下に埋める約束をしました。後には引けなくなった瞬間でした。
藍染はこうして石徹白洋品店の事業の一部になりました。蒅を安定的に手に入れるのは難しいこともあり(もちろん馨生里さんのこだわりもあり)、赤ちゃんをおぶって藍畑の手入れをする日々が始まりました。最初はどうして良いかわからないことも多く、苦労の連続だったそう。
そのうち、服のデザインで試行錯誤する馨生里さんのもとに、強力な助っ人が現れました。杉下ひとみさんとの出会いです。杉下さんは東京で有名なアパレルブランドのデザイナーとして働いていましたが、働きすぎで体を壊し、地元に帰省しているところでした。働きすぎだけでなく、ファッション産業から出る多大な廃棄物にも疑問やストレスを感じていました。ある時石徹白を訪れて、すべて天然の素材を用いてまったく廃棄物のでない服作りをする石徹白洋品店の取り組みを知り、これが自分の求めていたものだと、参画を決めました。2016年に石徹白洋品店に合流し、それまであった野良着ベースのパターンを、現代的で洗練されたものに作り替えました。

たつけをベースに服作りをするだけではなく、その知恵を世の中に伝えていきたい。そんな想いから、年に数回、たつけを制作するワークショップも開催しており、それを目当てに日本各地から石徹白洋品店に人が集まります。3日間のワークショップでは、自分の身体に合ったたつけの作り方を学び、また地元のお年寄りとの交流を通して地域の歴史や生活も学びます。その内容を知って、amirisuでもスタッフと一緒に参加しようと計画しています。状況が落ち着いたら、石徹白でリトリートができたら素敵だな、などと夢が広がります。
次第に失われつつある地域の歴史や古来からの知恵をお年寄りから学び、次の世代へ渡すことは、馨生里さんが大切にしていることのひとつです。地域のお年寄りから昔の暮らしぶりや人生について、そして古くから伝わる民話などを聞き取り、本を作っています。この地域に移住したい人々のサポートをしたり、石徹白に人を呼び寄せ、地域の良さを知ってもらうような活動も行っています。
石徹白洋品店はこの山奥の村にあって、地域の持続可能性を高め、人々が集い来る場所になりました。東京から、大阪からもとても遠い場所にありますが、日本の各地から失われた田舎の良さを体験しに、ぜひ訪れてみてください。サステイナブルな暮らしとは何かを考えるきっかけ、そしてスローファッションを考えるうえでの大きなヒントが得られると思いますよ。

写真2: 石徹白洋品店と平野夫妻の自宅。奥の高い木の向こうには白山連峰が見える。
写真3: 右が平野彰秀さんと馨生里さん。2020年3月に取材。(撮影:田中佳奈)
写真4: 糸を藍で染めた後、手機で生地を織り、仕立てられたたつけ。糸染めの美しさが生地に現れている。
写真5: 桜で染められたばかりの布たち。
写真6: たつけの作りかたを詳しく解説した本。店頭以外にも、オンラインショップなどで販売されている。最近キットも発売。
石徹白洋品店の様子。草木で染められた様々な色や風合いの服が並ぶ。